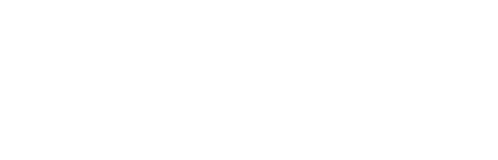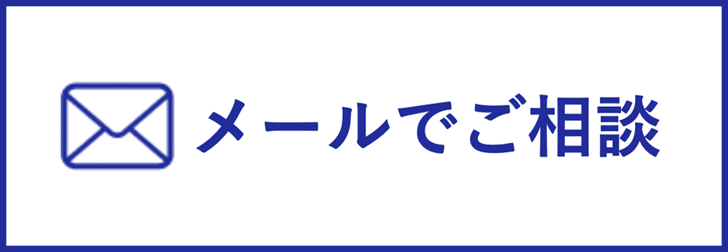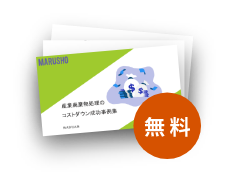目次
■ 廃プラスチックをめぐる環境は大きく変化している
かつては「廃プラ=燃やす・埋める」が一般的でした。
しかし、廃棄物処理コストの上昇やカーボンニュートラルへの社会的要求により、マテリアルリサイクル(再資源化)の重要性が急速に高まっています。
プラスチックは石油資源をもとに作られ、燃焼すればCO₂を排出します。
これを資源として再利用することは、資源循環の促進とCO₂削減の両立につながります。
■ マテリアルリサイクルを推進する3つのポイント
1. 排出段階での分別精度を高める
マテリアルリサイクルの最大の課題は「異物混入」です。
異なる樹脂が混ざる、金属・紙などの異物が含まれるだけで、再生原料の品質が大きく低下します。
→ 現場での材質別・色別分別ルールを徹底することで、再利用率が大幅に向上します。
2. 処理業者との情報共有を密にする
排出事業者がどのような種類のプラスチックをどれだけ出しているのか、処理業者がどのような再資源化ルートを持っているのかを双方向で共有することが重要です。
定期的な情報交換や、マニフェスト・契約書を通じた情報の可視化により、リサイクル可能な流れを構築できます。
3. 再生材の利用を社内にも広げる
廃プラのリサイクルは「排出を減らす」だけでなく、「再生材を使う」側に回ることでも循環が強化されます。
自社製品・梱包材・パレットなどに再生プラスチックを採用することで、循環経済への取り組みがより明確になります。
■ 法制度と市場の追い風
2022年施行の「プラスチック資源循環促進法」では、事業者に対し排出抑制・再資源化・再利用設計などが求められています。
また、再生プラスチックの需要拡大により、マテリアルリサイクルの市場価値も上昇傾向にあります。
この流れは今後さらに強まり、「燃やす」ではなく「使う」仕組みを早期に構築した企業が、コスト面・環境面の両方で優位に立つでしょう。
■ 廃プラスチックの未来を“資源”として見据える
マテリアルリサイクルを進めるには、排出段階から処理・再利用までの一貫したマネジメント体制が欠かせません。
「廃棄物を減らす」視点から、「資源を生かす」視点へ――企業の廃棄物戦略が、環境価値と経済価値の両立を実現します。
■ まとめ
- 廃プラを“燃やす”から“使う”へ転換する時代
- 分別精度・情報共有・再生材活用が成功のカギ
- 法制度・市場動向はリサイクル推進を後押し
もし、自社での廃プラスチック再資源化の仕組みづくりに課題を感じている場合は、
弊社の産業廃棄物コンサルティングサービスでサポート可能です。
現場調査から再資源化スキーム構築まで、一貫してご支援いたします。
ぜひお気軽にお問い合わせください。
※法人様のみのご対応となります。