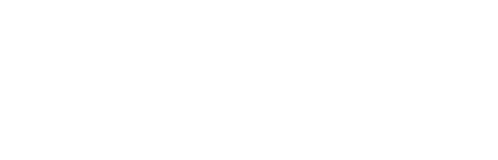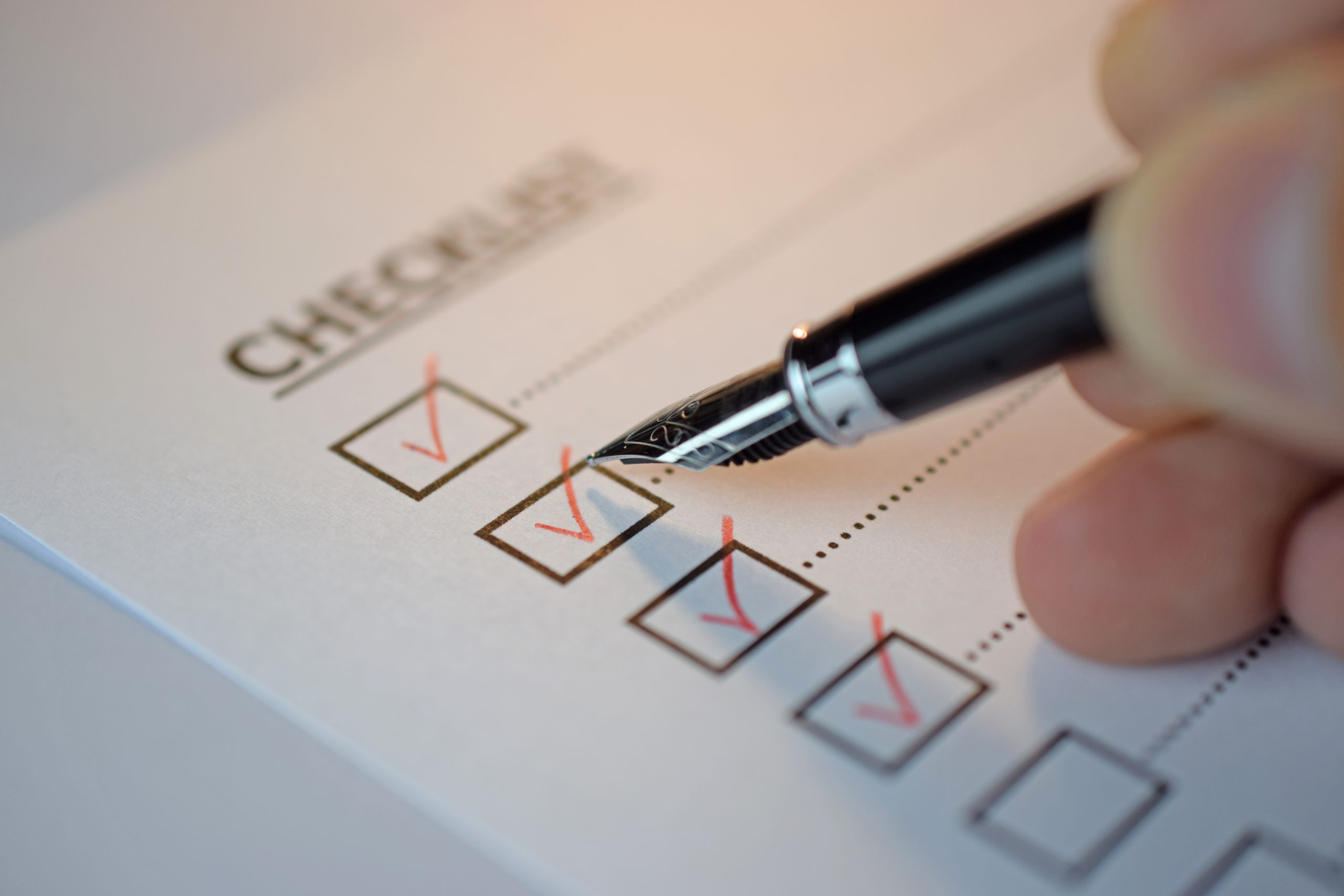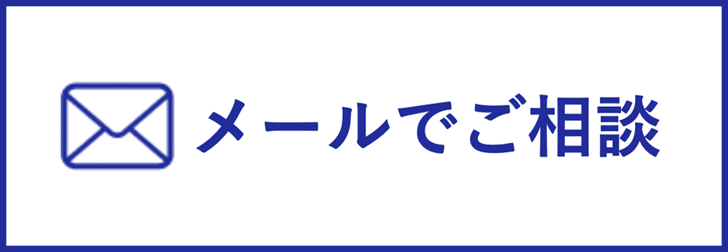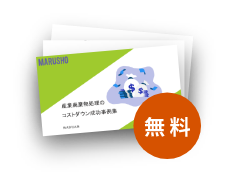新たに廃棄物処理をする、他の処理業者へ乗り換える場合などに廃棄物の詳しい情報が必要です。
新しく産業廃棄物を管理・担当される方で、どんな情報が必要なのかピンとこないかもしれません。
今回は廃棄物処理を依頼する際にどんな情報があればよいか?について解説していきます。
目次
具体的な必要情報

①廃棄物の法分類
そもそも許可を持っていない業者では処分・収集運搬ができないため必須情報です。
わからない場合は、管轄する行政機関に確認したり、発生工程や性状、成分、業種指定があるかなどから調べましょう。
②発生工程
どんな工程によって発生した廃棄物なのか重要な情報です。
③性状・荷姿
廃棄物は固体or液体で、どんな状態で保管されているのか。
他にも「臭いや付着物、汚れ、有害物質が含有されている」などがあった際、
回収した後に受け入れ拒否や返品、最悪の場合には事故などのトラブルになりかねません。
こちらも確認しておきましょう。
④排出場所
収集運搬費の算出のため、なるべく詳しく伝える方が良いです。
〇〇市内などざっくりしていると若干費用を高めに見られる場合があります。
また、回収場所を確認して廃棄物置き場まで入れる回収車両サイズに制限がある場合は事前に伝えておきましょう。
⑤排出頻度
一度きりのスポット的に排出されるのか、定期的に一定量が排出されるのかは一つのポイントです。
一度きりの場合は一式で出される場合もあり、やや曖昧な表現でもあります。
見積りが出た後にはしっかりと内容を確認しておきましょう。
⑥排出数量
排出頻度と併せて、スポットであれば全部でどれくらいの量があるのか。
定期排出の場合は一度にどれくらいの量が排出されるのか重要です。
処分場の処理能力や収集運搬車両の選定に必要です。
具体的な単位としては、キロ、トン、リットル、㎥、フレコンや〇ℓドラム缶が何個など。
⑦参考資料
WDSやSDS、成分分析シートなどがあるとベストです。
他にサンプルや現物写真だけで判断してもらえる業者もありますが、このあたりの判断基準は処分場によってまちまちです。
もし必要情報がなければどうなる?

情報量少なかったり、不確かな情報を伝えてしまうと処理業者も対応できるのか判断ができず拒否されがちです。
もし、出来そうであっても通常より高めの価格で見積り提示される可能性が高いです。
最悪の場合、違法な処理をされてしまう恐れもあり危険です。
また、口頭のみでは正確性に不安が残ります。
よって、メール等で詳しい情報や参考資料を必ず送って確認してもらいましょう。
万が一、トラブルがあった際にもエビデンスを残しておくことがよいです。
追加・補足で必要になる情報は?
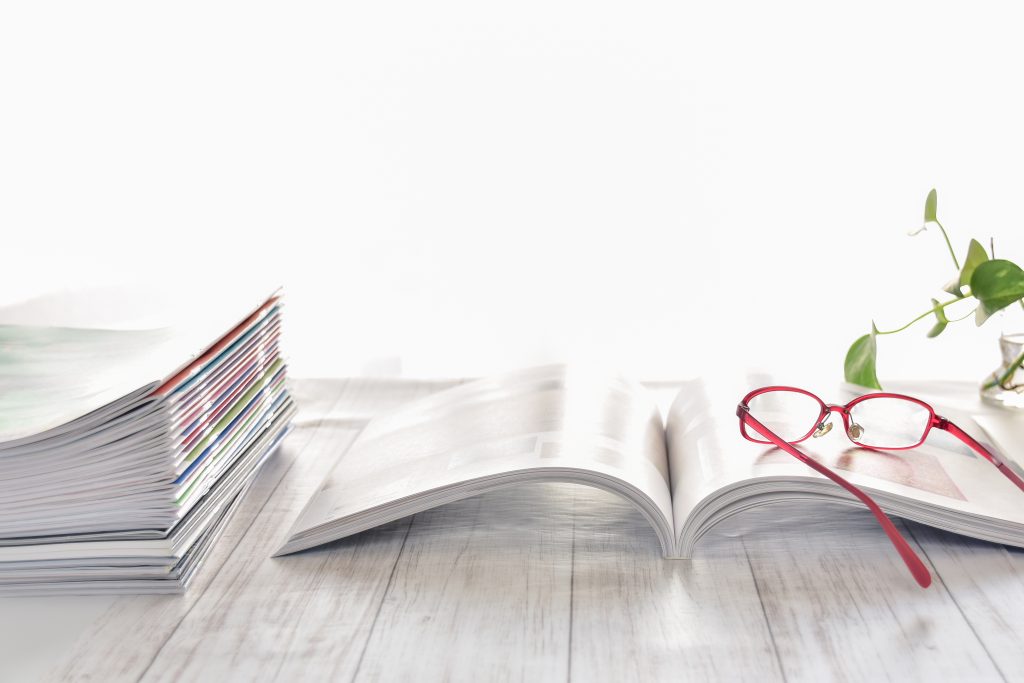
業者によっては、受入れ基準や費用算出にあたって追加で必要になる情報もよくあります。
例えば混合されている廃棄物で、何かどれくらいの割合で混ざっているか具体的にわかるとよいです。
また、分別が可能なのか?荷姿を業者指定の形へ変更が可能か?
対応可能な場合に受入れが容易になったり、費用削減にも繋がるケースがあります。
有価物化やリサイクルするにあたっては、どんな素材や単一素材で分けられているかなどの情報も重要です。
当社でもヒアリングの際に詳しく現状をお伺いさせていただきます。
情報量が多いほど、よりよいご提案をすることが可能です。
不明点や疑問点は、一つずつ丁寧にご説明いたしますのでお気軽にご相談いただけます。
これから廃棄物処理をされる、見直しの際などに是非ご利用ください。