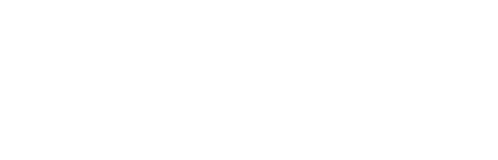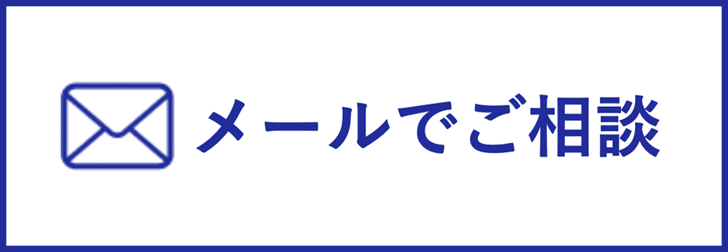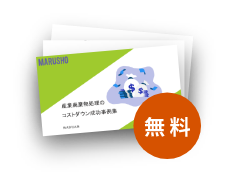近年、産業廃棄物に関する規制は年々厳格化しています。
廃棄物処理法では「排出事業者責任」が定められており、排出した企業は処理委託後も最終処分までの責任を負うことになります。
特に中小企業にとっては、十分な人員や専門知識が不足しがちなため、思わぬリスクに直面するケースも少なくありません。
では、どのようにして廃棄物リスクを管理すべきでしょうか。
目次
リスクを「見える化」する
まず大切なのは、自社からどのような廃棄物が排出されているかを正確に把握することです。
一般廃棄物と産業廃棄物の区分、さらには特別管理産業廃棄物が含まれていないかを整理する必要があります。
廃棄物の性状や量を見える化することで、処理ルートの妥当性を判断でき、リスク把握の第一歩になります。
信頼できる処理業者を選定する
委託先の不適切処理が原因で行政処分を受けたり、新聞報道で社名が公表される事例は後を絶ちません。
中小企業の場合、「価格が安い」という理由だけで業者を選んでしまうリスクが高まります。
許可証の有効性確認、処理施設の現地視察、実績の有無などをチェックすることが不可欠です。
契約書とマニフェストの適正管理
処理委託契約書は形式的に交わすだけでは不十分です。
処理方法や受け入れ条件、責任範囲を明確に記載し、自社の排出実態に即した内容であるかを確認しましょう。
さらに、マニフェストの交付・回収を徹底し、最終処分まで完結していることを追跡することが重要です。
これができていないと、知らぬ間に不法投棄に関与してしまうリスクがあります。
社内教育と定期的な監査
廃棄物管理は担当者だけの業務ではありません。
現場で排出に関わる従業員への教育を行い、誤った分別や不適切な処理を防ぐ体制を整えることが求められます。
また、年に1回は委託先の処理状況を監査するなど、継続的なチェック体制を築くことが有効です。
まとめ
中小企業における廃棄物リスク管理は「コスト負担が大きい」と敬遠されがちです。
しかし、不適切処理による行政罰や企業イメージの毀損を考えれば、むしろ事前の管理体制構築こそが最大のリスク回避策といえます。
限られたリソースの中でも、廃棄物の見える化・信頼できる業者の選定・契約書とマニフェストの適正管理・教育と監査を着実に実行することで、中小企業でも十分にリスクをコントロールすることが可能です。
廃棄物の管理やお困り事がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
※当社は法人様のみの対応となります。