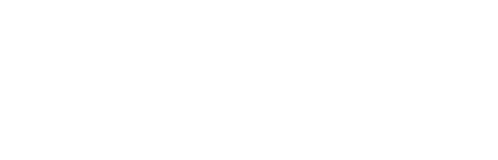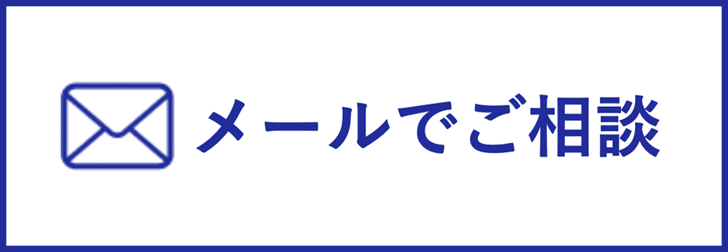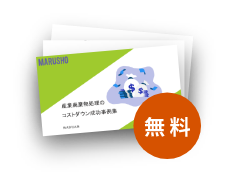目次
はじめに
企業が産業廃棄物を処理する際には、「廃棄物処理委託契約書」の締結が法律で義務付けられています。
しかし、形式的に契約書を作成して終わりにしてしまうケースも少なくありません。
実はここに、大きな法令違反リスクやコスト増の原因となる「盲点」が潜んでいます。
本記事では、企業が廃棄物処理委託契約で見落としがちなポイントと、実務での対策を解説します。
委託契約書の更新忘れ
廃棄物処理委託契約には「有効期限」があります。
通常は5年以内の更新が必要ですが、更新を怠ると契約書が失効し、無契約状態での委託=法令違反となります。
廃棄物処理委託契約には「有効期限」があります。
通常は5年以内の更新が必要ですが、更新を怠ると契約書が失効し、無契約状態での委託=法令違反となります。
よくあるケース
- 契約は昔に結んだまま、更新日を把握していない
- 担当者が異動して引き継がれていない
- 複数拠点で業者がバラバラ → 一元管理できていない
対策
- 契約更新日を管理台帳やシステムで一括管理
- 契約の有効期限をリマインドする仕組みを導入
委託内容と実際の処理が一致していない
契約書には「処理区分」「処理方法」「処理施設」が記載されます。
しかし、現場では次のようなズレがよく起こります。
- 契約書では「焼却」と記載 → 実際は「中間処理後に埋立」
- 契約上は「産業廃棄物」 → 実際は「特別管理産業廃棄物」だった
- 契約書にない品目を現場で追加している
これらは契約違反・法令違反となる可能性があり、企業側も責任を問われます。
対策
- 定期的に処理フローを確認し、契約内容と照合
- 新しい廃棄物が発生した場合は必ず契約追加
処理業者任せにしてしまうリスク
「業者に任せているから大丈夫」と思っていても、万が一不適正処理が発覚した場合、排出事業者責任が追及されます。
実際の事例
- 委託先業者が不法投棄 → 排出企業がマスコミに報道され、信用失墜
- 契約書はあるが、委託区分に誤り → 行政指導を受けた
対策
- 委託業者の許可証を定期的に確認(期限・品目・処分方法)
- マニフェストと契約内容の整合性を点検
- 年1回の業者監査をルール化
まとめ
廃棄物処理委託契約の盲点は、
- 契約更新の失念
- 契約内容と現場の不一致
- 業者任せによるリスク放置
の3点に集約されます。
契約書は単なる「書類」ではなく、法令遵守と企業リスク管理の基盤です。
自社の委託契約を見直すことで、法令違反の回避だけでなく、廃棄物処理コストの最適化や取引先からの信頼向上にもつながります。
今こそ「契約の棚卸し」を行い、自社の廃棄物管理を万全にしましょう。