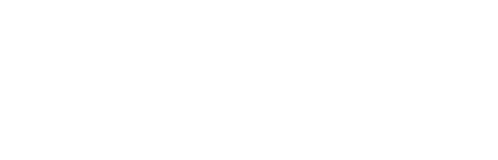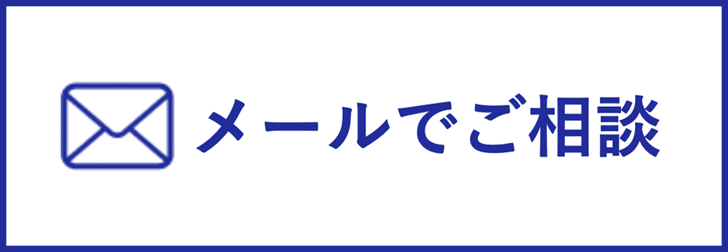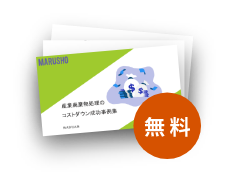廃プラスチックは、海洋プラスチック問題など地球規模での問題を抱えています。
廃棄量を減らすことや積極的にリサイクルに取り組むことが重要ですが、廃プラスチックの有価物化はできるのでしょうか?
こちらのコラムでは、廃プラスチックのリサイクルと有価物化について解説いたします。
目次
廃プラスチック類とは?
廃棄物分類の一つである『廃プラスチック類』は、事業活動に伴って排出されるプラスチックのことで、「合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状・液状のすべての合成高分子系化合物」とされています。
具体的には、使用済みの食品トレイや容器、スプーンやフォーク、ペットボトル、ビニールシート、包装フィルム、PPバンド、コンテナケース、発泡スチロール、廃タイヤなど。
基本的に製品そのもの、または材料にプラスチックが含まれているものです。
廃プラスチックのリサイクル
廃プラスチックのリサイクル方法は大きく3つあります。
1)マテリアルリサイクル/廃プラスチックを材料として、新たな製品に活用します。
2)ケミカルリサイクル/廃プラスチックを科学的に処理し、原料にしてから再利用します。
3)サーマルリサイクル/廃プラスチックを焼却する際の熱エネルギーを回収して利用します。
廃プラスチックの処理には問題があります。
廃棄されたプラスチックによる海洋汚染問題。
2017年以降、中国を始めとするアジア各国で廃棄物の輸出規制が敷かれたことなどからも、自国でのリサイクルが重要課題になっています。
有価物化できる廃プラスチック
廃棄処理するだけでなく、廃プラスチックは有価物化することも可能です。
有価物化できるものの例としてはいくつかあります。
・ポリエチレン(PE)/ボトルキャップ、袋など
・ポリプロピレン(PP)/包装材、食品容器など
・ポリエチレンテレフタレート(PET)/ペットボトル、食品容器など
・ポリ塩化ビニル(PVC)/ビニールシート、サッシなど
・ポリスチレン(PS)/食品トレイ、カップなど
しかし、全ての廃プラスチック類が有価物化できる訳ではありません。
汚れや残渣がひどいもの、異なる材料が混合しているもの、劣化が激しいもの、有害物質を含んでいるものなどは買取りできないものもあります。
廃棄物の有価物化は、処理コストを抑えるだけでなく利益を生むこともできます。
そのためには、日頃から分別を徹底しておくなどが必要です。
分別の方法、リサイクルの取り組み、有価物化可能かの判断、業者の選定などトータルでご提案いたしますので、ぜひご相談ください。