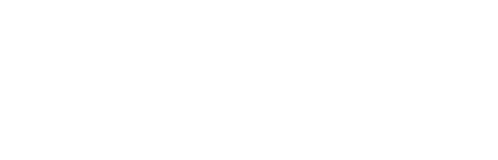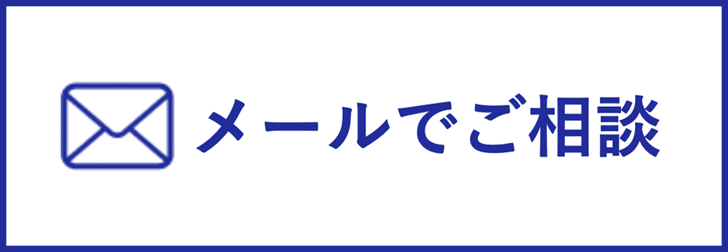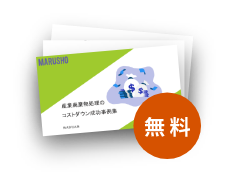産業廃棄物コンサルタントが現場で感じる“処理困難物”のリアル
産業廃棄物を取り巻く現場では、年々その内容が複雑化し、「これってどこに出せばいいの?」「どの処理業者も受けてくれない…」というご相談が増えています。
私たちのもとにも、いわゆる「処理困難物」に関する相談が後を絶ちません。
そもそも「処理困難物」とは、明確な法律用語ではありません。
しかし、現場では「通常の産廃処理ルートでは処理が難しいもの」「処理先が非常に限られているもの」として認識されています。
では、なぜ一部の廃棄物は“処理が困難”とされてしまうのか?
今回は、現場で実際に感じる3つの主要な要因からその本質を紐解いていきます。
目次
【物理的・化学的な性質】──「燃えない・壊れない・反応する」
処理困難物の代表例としてよく挙げられるのが、以下のような廃棄物です。
・FRP(繊維強化プラスチック)
・廃石膏ボード
・アスベスト含有廃材
・高濃度の油分や薬品を含む泥状物
これらに共通するのは、「処理工程が難しい」あるいは「安全性が確保できない」という特性です。
例えば、FRPは強度がありすぎて破砕できず、また燃焼時に有害ガスが出るため、一般的な焼却施設では受け入れ拒否されることが多くなります。
また、pHの極端に高い・低い廃液や、発熱性・反応性をもつ廃酸・廃アルカリなどは、運搬や保管にも注意が必要で、処理を請け負える許可業者自体が少ないのが現状です。
【処理インフラの不足】──「処理できる業者が限られている」
物理的性質に加え、インフラ面での課題も大きな要因です。
全国的に見ても、特殊処理を要する廃棄物の対応施設は非常に少なく、特に地方では処理先が皆無というケースも珍しくありません。
たとえば、FRPのリサイクル施設や、廃石膏ボードの再資源化設備は、処理先がかなり限られており、地方企業が処理しようとすると「運賃の方が処理費より高い」という事態も起こります。
加えて、処理単価も高額で、「1kgあたり数百円」というケースもざらです。
排出者としてはコスト負担が大きく、処理を後回しにするか、保管し続けるケースもあります(いずれも望ましくありません)。
また、業者側にとっても、受け入れに技術や許可が必要でありながら、量が少なければ採算が合わないというジレンマもあります。
【法規制・責任の所在】──「グレーゾーン」と「責任回避」
三つ目の要因として見過ごせないのが、法制度とのギャップです。
たとえば、アスベスト含有廃棄物やPCB含有物のように、法的な特別管理が必要なものに該当するかどうかが微妙なケースでは、処理業者が万が一を恐れて受け入れを拒否することも多くあります。
また、製品の解体時に出る「混合物(複合材)」や、「家庭用と見なされるような形状の廃棄物」などでは、“一般廃棄物扱いか産廃かの判断”がつきにくいこともあります。
この“グレーゾーン”に分類される廃棄物は、扱いに慎重にならざるを得ず、排出者・処理業者ともに「判断がつかないから、手をつけにくい」状況を生み出してしまいます。
さらに、誰がどう責任をもつかが不明確なケース(例:解体工事で見つかった保管品、廃校で放置された薬品など)では、「うちの責任ではない」として処理が放置されがちです。
処理困難物の問題は、社会全体で向き合うべき課題
処理困難物は、排出事業者・処理業者のいずれか一方だけが解決できる問題ではありません。
私たちコンサルタントの立場では、以下のような提案をよく行います:
- 排出事業者:事前に処理先やルートを確認し、困難物が混入しないように設計段階から配慮する。
- 処理業者:処理困難物の傾向を把握し、少量でも受け入れられる体制を検討する。
そして、私たちコンサルタントは、その”つなぎ役”として、情報を整理し、選択肢を提示し、現場に即した解決策を提案し続けています。
処理困難物を“困難”のまま放置しないために
技術が進んでも、処理困難物はゼロにはなりません。
だからこそ、各立場が連携し、「処理困難」を事前に予見し、対応できる体制をつくることが重要です。
もし、処理先に困っている廃棄物があれば、ぜひ一度ご相談ください。
専門的な知見と全国ネットワークを駆使し、“何かしらの突破口”を探しご提案いたします。