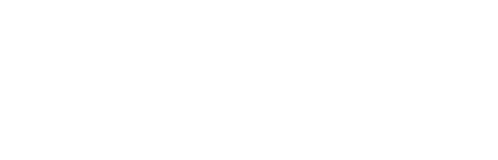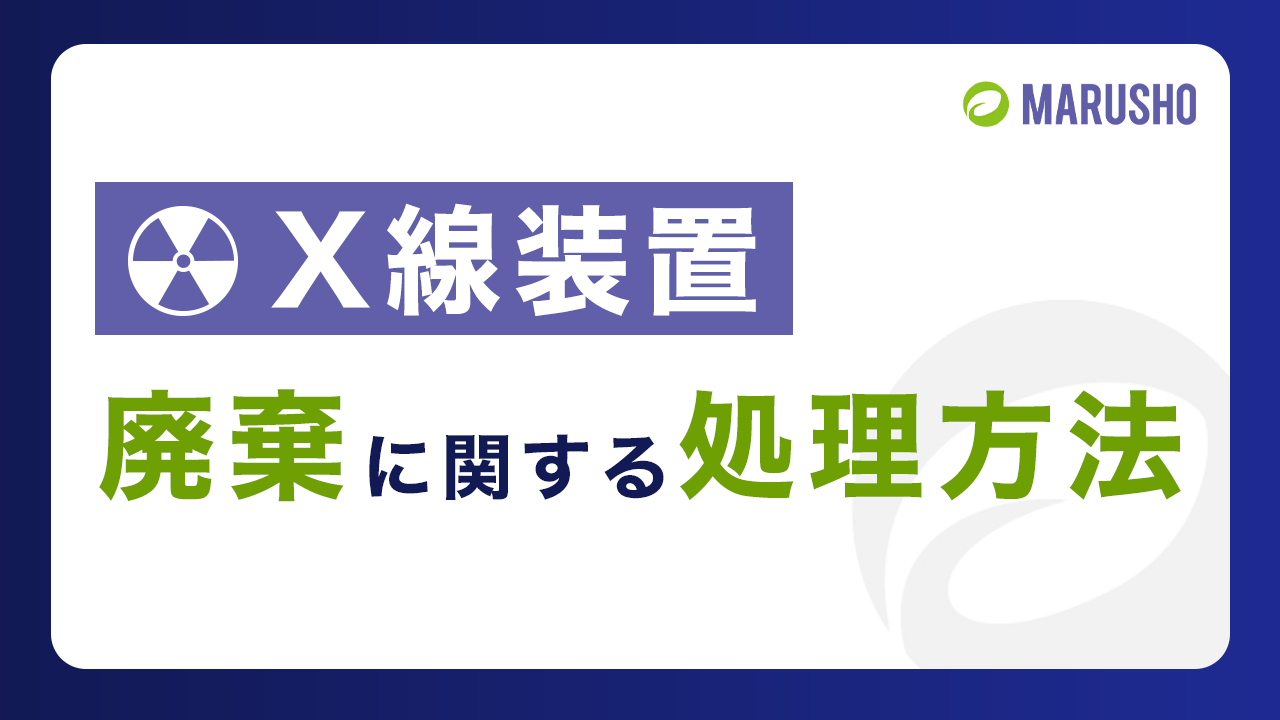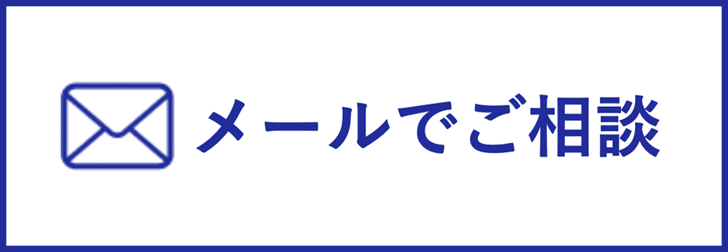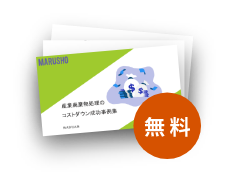X線装置は、主に医療や研究所で使用されていたものが廃棄されます。
例えば、蛍光X線回析装置・レントゲン装置・ポータブルX線装置などがあります。
これらのX線装置は、全て産業廃棄物として処理する必要があります。
しかし、「どう処理していいのか分からない」とお悩みを抱えている企業様が多いです。
本記事ではどういった点に気をつけて処理すればよいのか解説していきます。
こちらを是非参考にして処理方法を検討してみてください。
当社でもX線装置の処理ご提案を承っております。
廃棄・処理でお困りの際は是非ご相談ください。
目次
X線装置に含まれる有害物質とは


装置に内蔵されているX線管球の窓材に、「ベリリウム」という金属が使用されています。
X線管の形状は装置・メーカーによって様々です。
ベリリウムが使用されている量はわずか数グラム程度とかなり少量です。
しかし、ベリリウムは人体に有害な金属で毒性があります。
もし、例えば粉塵を吸ってしまうと肺機能に障害を及ぼす恐れがある危険な物質です。
毒性が高い一方で、法律上は特別管理産業廃棄物には該当していません。
その特殊性から適正に処理ができる施設も限られます。
また、遮蔽部に鉛、冷却に絶縁油を使用している装置はさらに注意が必要です。
古い装置の絶縁油にはPCBが含有されている可能性があります。
製造年月を確認して、可能性のある場合はメーカーか分析業者へ相談しましょう。
PCB廃棄物の処理期限について詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
これらが装置に含有している場合、処理できる施設はかなり限られますのでこちらも注意してください。
それらを除けば、X線装置はほとんどが鉄やステンレスなどの一般的な金属で構成されています。
X線装置から有害物質を取り出す方法は?

X線装置の解体はドライバーなどの一般的な工具を使用して解体可能です。
解体に必要となる廃棄資料や構造図面は、メーカーや販売元で取り寄せる事ができます。
しかし、X線装置に含まれる「ベリリウム」や「鉛」「絶縁油」は非常に危険な物質です。
基本的には、信頼する処理業者に相談や解体作業の依頼するのが良いでしょう。
特に製造年が古いものは資料が残っておらず、メーカーも廃業していることがあります。
このような場合や、大型の装置などの場合も重量があり解体が難しいです。
よって、メーカーや処理業者にどのように処理するかを相談しましょう。
X線装置の情報が何もない場合は?

まず、故障したX線装置をそのまま放置することは、医療法で禁止されています。
X線装置は、廃止届が出るまでは例え故障している装置でも正常な装置同様、日常点検や漏洩線量測定等の実施が必要となります。
故障したX線装置は、装置を廃棄処理し廃止届を提出するか、修理をして使用可能な状態にしておきましょう。

しかし、稀に何も情報がないX線装置もあります。
・故障等の理由で長年放置された。
・担当者も転々とした結果、誰もわからない。
こういった理由が背景にあるようです。
何が使用されているか不明な装置は、処理場から受入れを拒まれやすいのが現状です。
何も情報がない装置の場合は、どうしたらよいでしょうか。
・メーカーや処理実績のある処理場と相談する。こちらが最も安全です。
・解体する場合「ベリリウム」「鉛」などの有害物質に直接触れないよう対策する。
対策を万全にして慎重に行いましょう。
X線装置を処理業者に依頼する方法
処理業者に依頼する場合は、X線装置の廃棄にあたってどんな有害物質が使われているか、メーカーや販売元に確認して形状や重量などわかる情報を処理先へしっかり伝えましょう。
物によっては処理先でそのまま引き取って、解体・処理してくれる可能性もあります。
また、ベリリウムは毒性の強い物質ながら特別産業廃棄物には指定されていません。
使用されている量もかなり微量と侮って、他の廃棄物に混ぜるといった不適切処理は絶対に行なわないようにしましょう。
まとめ
X線装置の廃棄処分は、危険なものが含有しており、自らの知識や自己流で行うことは大変危険です。
自分で解体する前にメーカーや処理業者にどのように処理するかを相談することをおすすめします。
相談する業者がいないという方は、当社でもご相談を承っております。
当社は、メーカーとも連携して廃棄X線装置の処理に取り組んでいる実績があります。
写真しかないような物でも、解体や分析調査も含めたご提案を承ります。
X線装置の廃棄でお困りの際は是非ご相談ください。
実績紹介はこちら!